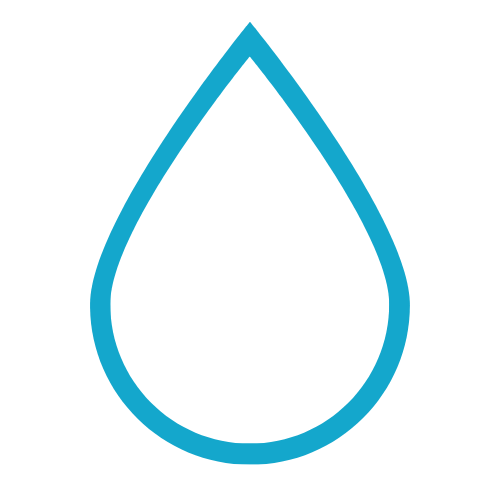06_工事業者を決定|正しい相見積もりの取り方と比較のコツ
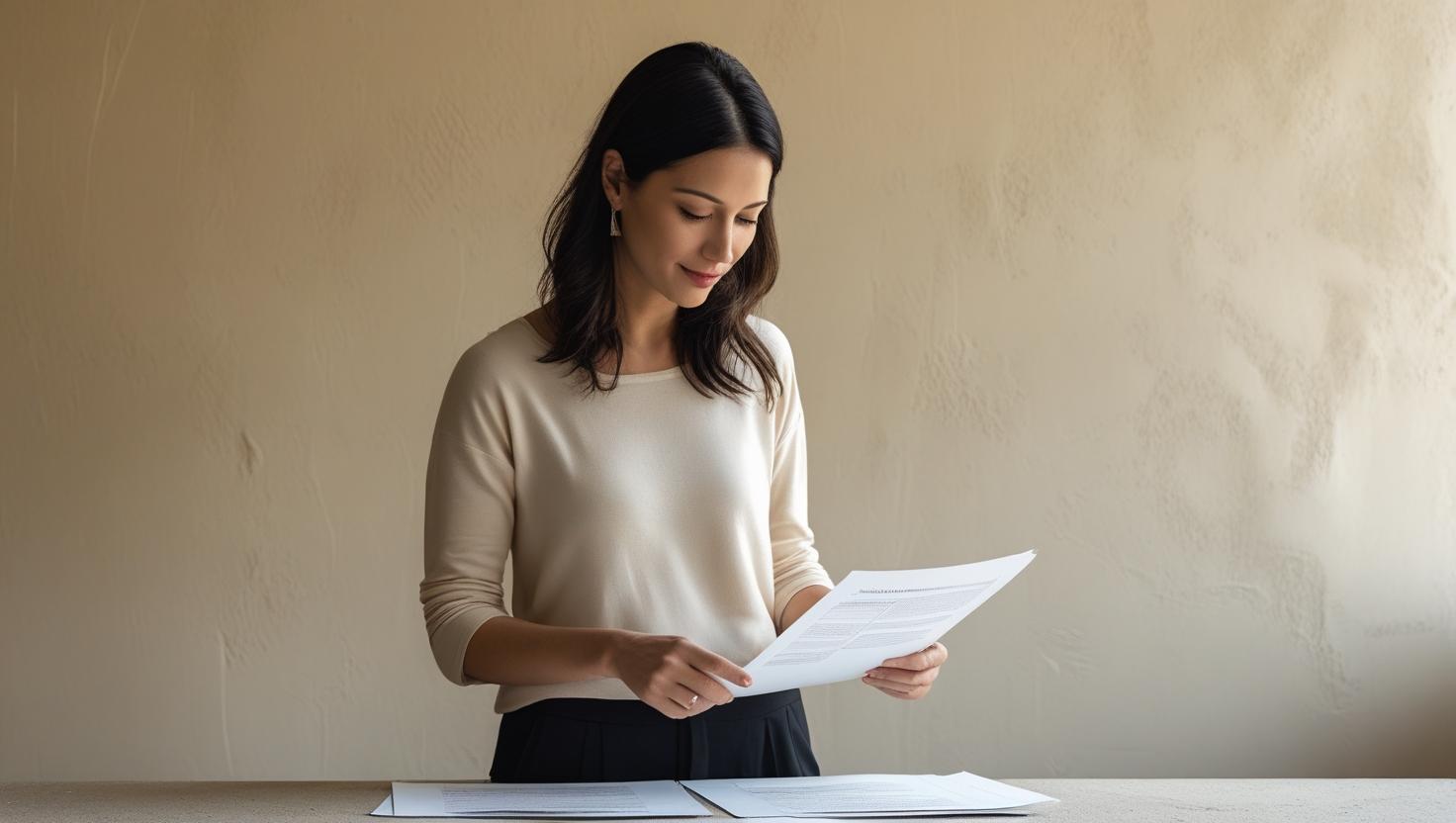
furuhiro
納得できる工事を進めるには、見積の“中身”を比べることが大切
相見積もりとは?
相見積もり(あいみつもり)は、複数業者から見積を取って比較する方法ですが、正しい取り方をしないと意味がありません。
相見積もりの種類
相見積もりには以下の2種類があります。
理想的な相見積もり
- 各社に独立して見積を依頼する
- 各業者が独自視点で工法・金額を提案
- 業者ごとの考え方や対応姿勢も比較できる
結果として公平性があり、依頼者の利益を最大化できます。これが本来あるべき「相見積もり」の形です。
形式だけの相見積もり
- 最初に1社と調整後、形式的に他2社の見積を用意する
- 実質は1社主導の提案のみで、他社は添え物扱い
- 比較にならず第三者性もなくなる
呼び名は「相見積もり」でも効果は全く異なります。
一括見積サイトの注意点も知っておこう
最近では、一つの見積サイトで「3社まとめて見積もりが取れる」便利なサービスもあります。これらは基本的に各社が独立して見積を出しているとされていますが、すべてがそうとは限らない場合もあるため注意が必要です。
もし万が一、裏で調整されていたり、実質的に一社主導のような形になっていた場合には、本来の相見積もりの効果が得られません。より安心したい場合は、自分でも一社を別に選んで直接見積もりを取るのがおすすめです。
「形式だけの見積もり」を見分ける方法
相見積もりを取ると、各社で見積書の書式やレイアウトが異なるため、内容がバラバラに見えることがあります。しかし、その中でも「形式だけの見積もり(=本気で工事を請ける気のない見積)」は、ある特徴で見分けることができます。
- 他社と項目内容・仕様・数量が完全一致
- 各社で調査の仕方や拾い出し(積算)方法には個性が出るのが普通です。にもかかわらず、項目内容がそっくり同じで、単価と合計金額だけが違う場合は要注意です。
- 自社視点・提案が反映されていない
- 本来、現地調査をもとに「この工法がよい」「ここは補修不要」などの提案があるはずです。それがなく、他社の構成をそのままコピーしたような見積書は、価格競争用の“比較資料”としてだけ出されている可能性があります。
「見やすいから信頼できる」ではなく、「内容に個性がないから疑ってみる」ことも大切です。形式だけの見積もりは、見た目がきれいで比較しやすい反面、責任をもって工事をする意志がないケースもあるので注意しましょう。
まとめ
相見積もりは「数を揃える」ことではなく「適切な比較材料を集める」ための手段です。3社以上に独立して見積を依頼し、価格だけでなく対応・提案も比較しましょう。また「形式だけの見積もり」には要注意です。正しい取り方で、納得できる修理を進めましょう。
ABOUT ME