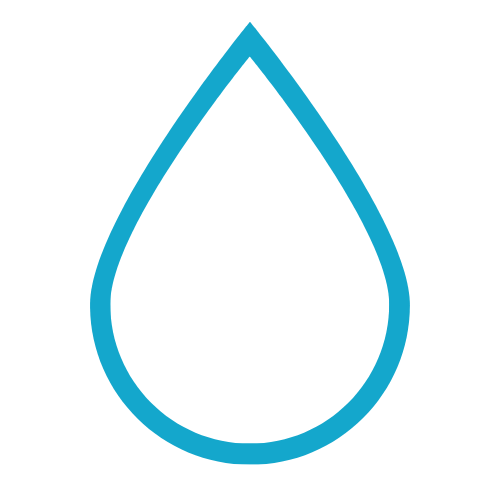05_相談先を選ぶ|「雨漏り診断士」とは?信頼できる専門家の見極め方

furuhiro
目次
第三者の視点で正確に診断してもらうには?
雨漏り診断士とはどんな資格か?
雨漏り診断士は、NPO法人「雨漏り診断士協会」が認定する民間資格で、雨漏りの原因を特定し、最適な対処法を提案する専門家です。受験に学歴・職歴制限はなく、20歳以上なら誰でも受験可能。ただし、実際には建築や施工に従事している技術者が大半を占めると考えられます。
雨漏り診断に資格は必須か?
雨漏り診断士がいなくても診断は可能ですが、第三者性や客観性が求められる場面では有資格者の関与が安心です。雨漏り診断士は「公正中立な立場で診断を行い、適正な雨漏り診断を提供する」という理念で活動しており、
- 資格を持っていること自体が知識や技術水準を満たしている証拠
- 実績や説明力も確認できれば、より信頼性の高い選定が可能
となります。
雨漏り診断の必要性
雨漏りを根本から解決するには、まず正確な原因を見極めることが何よりも重要です。原因を取り違えたまま修理を行ってしまうと、たとえ一時的に雨漏りが止まっても、数ヶ月後や数年後に再発する可能性があります。
人が体調を崩せば医師の診察を受けるように、建物も異常があれば専門的な診断が必要です。「診断 → 方針 → 検証」という流れを踏むことで、確実な対処と再発防止につながります。
雨漏り診断の基本ステップ
NPO法人雨漏り診断士協会が推奨する診断の流れは以下の通りです。
予備診断で立てた仮説を、1次・2次診断で検証し、必要に応じて3次診断へ。
診断は段階的に進めることで、誤診や過剰工事を防ぎ、確実な修理につながります。
- 予備診断【事前準備・仮説立て】
- 図面やヒアリング、建物履歴をもとに情報収集。
- 「どこから、なぜ漏れているのか」を仮定。
- 目的:1次・2次診断で検証するための方針づくり。
- 1次診断【非破壊|目視・触診など】
- 仮説に基づき、目視・触診・赤外線などで現場を観察。
- 散水は行わず、濡れた痕跡や劣化状況などから原因範囲を絞る。
- 目的:2次診断での検証対象を決定する。
- 2次診断【非破壊|散水調査】
- 絞り込んだ部位に散水し、再現性を確認。
- 散水時間の目安:木造・鉄骨造:90分 / RC造:120分
- 条件管理が重要(時間・位置・量など)。
- 3次診断【破壊あり|試験解体・通水】
- 2次診断で特定できなかった場合に実施。
- 仕上げ材の撤去や通水で構造内部を確認。
- 最終手段のため、必要性とリスクの判断が不可欠。
雨漏り診断士を探すには?
NPO法人雨漏り診断士協会公式サイトの「登録者一覧」から都道府県別に診断士を検索できます。診断士の氏名・所属企業・URLなどが掲載されています。
雨漏り診断士協会公式サイト
https://www.amamorishindan.com/
雨漏り診断士協会とは?
診断士の養成・教育、診断技術の普及を目的とするNPO法人です。雨漏りを社会課題と捉え、第三者的立場で公平な診断を提供する仕組みづくりを行っています。
他の資格との違い
雨漏り診断士の他にも「雨漏り鑑定士」など名称・試験要件が異なる民間資格がありますが、いずれも「雨漏り原因の特定と適切な対策提案」を目的としています。大きなくくりでは同じ役割を担う資格なので、業者選びの参考にするとよいでしょう。
まとめ
雨漏り診断は資格がなくても可能ですが、第三者性や客観性を重視するなら雨漏り診断士がいる業者に相談するのがおすすめ。資格の有無だけでなく、説明内容や過去実績を含め総合的に判断することが大切です。
ABOUT ME